

この会社は世界のライフサイエンス・医療診断機器分野のグローバル企業の日本法人として設立され、日本国内ににけるセールス&マーケティングを展開しています。
話し手
外資系医療機器メーカー
元人事総務部長
原田 あけみ 様
外資系医療機器メーカー 元人事総務部 部長 原田明美 様
聞き手

チームビルディングを行う前までの会社の状況は?
話し手)原田さん
当時私の人事部でのミッションの一つにエンゲージメントの改善がありました。
日本はハイグロスマーケットで毎年10%成長を求められます。日本法人は優秀な人材も多く施策を打ち出しながら頑張って成長していくのですが、当時は数値目標を設定し達成していくことはお手のものの営業部隊でありながらも「いつまで頑張ればいいのか」という社員の疲弊感を日々強く感じていました。
この状態から脱去しなければならない。そのためには「数字以外でこの会社で働く意味やこの職場の価値を伝える言葉や共通言語の必要性」を強く思ったのです。いわゆる「理念」ですね。当社はグローバル企業なので共通するタグラインはあったのですがそれはもちろん英語であり、日本語での共通言語にするには至っていませんでした。
なぜトゥーリアにチームビルディングワークショップの依頼をしたのでしょうか?
話し手)原田さん
先に話したように私がやりたいことは明確でしたので色々な経営コンサルやコーチング会社に問い合わせましたが、先方から出されるのは私たちがやりたいことへの提案ではなく、先方の持っているメニューを提示されることが続き、辟易していた時に山屋さん(トゥーリア)を思い出しました。彼女とは外資系ホテル人事部時代の同僚という既知であり、独立してコーチング関連の仕事をしていたことを思い出したのです。彼女なら自分たちの思い描くことを形にしてくれるのでは、と思い数年ぶりにコンタクトを取ったのが最初です。チームビルディングを実施する至る前に、組織のコミュニケーションの改善に取組んでおりました。まずは、組織の会議、情報共有の方法です。
トゥーリアはとにかく私の想いや当社の課題、そしてこれからやりたいと思う未来のビジョンに合わせて、我々がイメージする「チームビルディング」を検討し何度も提案してくれました。以前は社員に対して会社の目標や進捗状況が共有されず、情報の開示も制限されていました。しかし、情報を理解してもらうことの重要性を説明し、情報開示を進めた結果、社員からはよりタイムリーな情報提供の要望が増え、部門ごとに短時間の情報共有ミーティングが行われるようになりました。
それまでの会社とは1、2回のMTGまでしか進まなかったのですが、トゥーリアとは何度も、時には関連部署を交えて打ち合わせをさせていただき満足できるカリキュラムを構築してもらい、期待感と共に当日を迎えることができました
実際にどんなチームビルディングワークショップだったのでしょうか?
話し手)原田さん
参加者は日本法人の社長を含むリーダー職以上の幹部13名、2日間(10〜17時)で実施されました。当初参加者はこのチームビルディングを目的としたワークショップに懐疑的な空気がありましたが、初日半日で参加者間のバリアが解けました。同時に心地よい一体感と安心感が生まれ、個々が自発的に意見を出し合うようになりました。トゥーリアは我々の言葉を拾い上げ深堀りしながら再度チームにパスを渡し、整えていく。その過程でどんどん自分たちの輪郭がハッキリしていく、という時間は、参加者にとってあっという間の二日間であり、ものすごい集中力を必要とするワークの連続にも関わらず全員エネルギーが途切れることなくやり切った!という非常に充実した時間でした。とにかくセッションでの脳の使い方がいつもの仕事とは全く異なるので、いい意味での心地よい疲れが出るようなワークショップであったと好評でした。先に話したように、私にとってやりたいことは明確でした。いろいろな経営コンサルやコーチングの会社に問い合わせをして、やりたいことを伝えるのですが、先方から出されるのは、私達のやりたいことに対する提案ではなく、先方の持っているメニューが単に足し算や掛け算で提示されることが続き、なんかもとめているものと違うだよなと感じていたんです。そんなとき、20代くらいの頃、札幌のホテルで同僚だった山屋さんのことを思い出しました。たしか、コーチングで独立していたっていってたなと記憶していました。そして、私達がもとめているのは、ツールやソリューションの提案ではなく、私達の思いや心を傾聴して、みんなの話を引き出し気づきをまとめてくれることだよなと考えたときに、あの山屋くんならなんかうちのチームに入り混じってぐちゃぐちゃやってくれそうな気がして連絡してみました。
そして目的であった理念の構築まで2日間でたどり着くことができました。実のところ「2日ではチームビルドの土台はできても理念の構築までは無理だろう」と思っていたのですが、トゥーリアはやり切ってくれました。
この日私たちはグローバルのタグライン(英語)を、自分たちの仕事と徹底的に向き合い意見をぶつけ合いながら我々の言語である日本語で自分たちの言葉で新たに産み直しました。それはグローバルのタグラインであることは変わらずも、我々日本法人にとっての力強い「理念」になり、参加者1人残らず達成感と誇らしさが醸し出されていった、そんな時間でした。
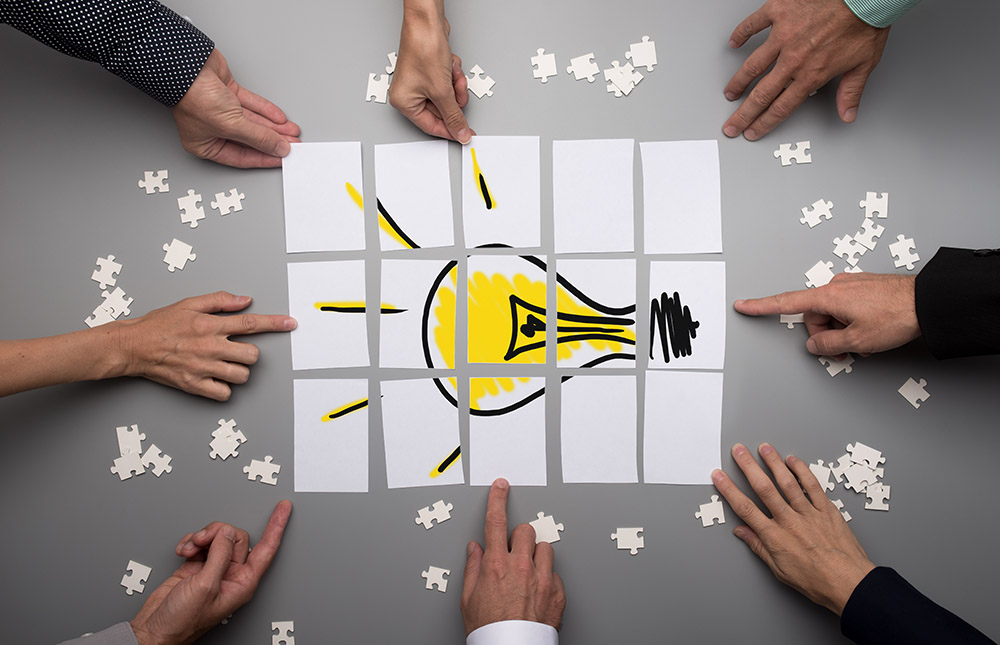
チームビルディングがもたらした効果はありましたか?
話し手)原田さん
効果は大きかったと感じています。ワークショップで生まれた言葉が、参加したリーダーたちを通じて各部門、社内に展開されました。各部門ではさらにこの言葉の意味を議論し、株主や顧客視点から「自分たちはどうありたいか」を考え、アクションプランに落とし込みました。全社的にも今後3年の方向性として発表されるなど、この言葉を軸に社員の意識が変化しました。自分たちで納得して生み出した言葉だからこそ浸透し、単なる目標ではなく「お客様への誓い」として働き方そのものがよりお客さま志向へと変化したのだと思います。日本法人のリーダー以上の幹部12-13名で2日間朝10時から夕方7時まで通しで実施しました。参加者にとってはあっと言う間で、全員がエネルギーは途切れずやりきったというこのでした。とにかく、セッションでの脳の使い方がいつもの仕事とは全く違うので、いい意味での心地よい疲れが感じられるセッションと好評でした。そして、最終的には目的だった理念もみんなでつくりあげることができました。ここでみんなで産み出した言葉は「お客さまの行動に真実を」です。クライアントに自信をもって伝えられる自信のある言葉となり、参加者一人残らず達成感と充実感そして誇らしさが醸し出されていたんです。
またグローバル本社との関係にも変化が見られました。リーダーたちが前向きに行動し部門間で連携しながら本社への伝え方を工夫するようになり、日本の要望が品質向上に役立つと理解され、意見がより積極的に受け入れられるようになりました。セッションのはじめですが、今回参加したリーダーたちもそれぞれが人間関係があったわけでもなくコロナ禍ということもあり、ちょっとお互いが疎遠が感じの雰囲気ででした。そして、組織として縦のコミュニケーションがとれていないので、いきなり社長も含めたセッションがはじまり、あるリーダーとかは社長への違和感とかは伝わってきたのは覚えています。
こうした前向きな組織への変化の結果、営業成績も上がり続け日本法人としての存在感も回復しました。
働く拠り所となる理念を共通言語として会社全体で共有し、数字だけを追う疲弊感のある働き方から脱却したことで、社員の意識や行動が変わったことが大きな要因だと感じています。そのような意味でチームビルディングワークショップはその確かな一歩であったと思っています。